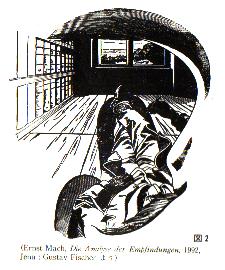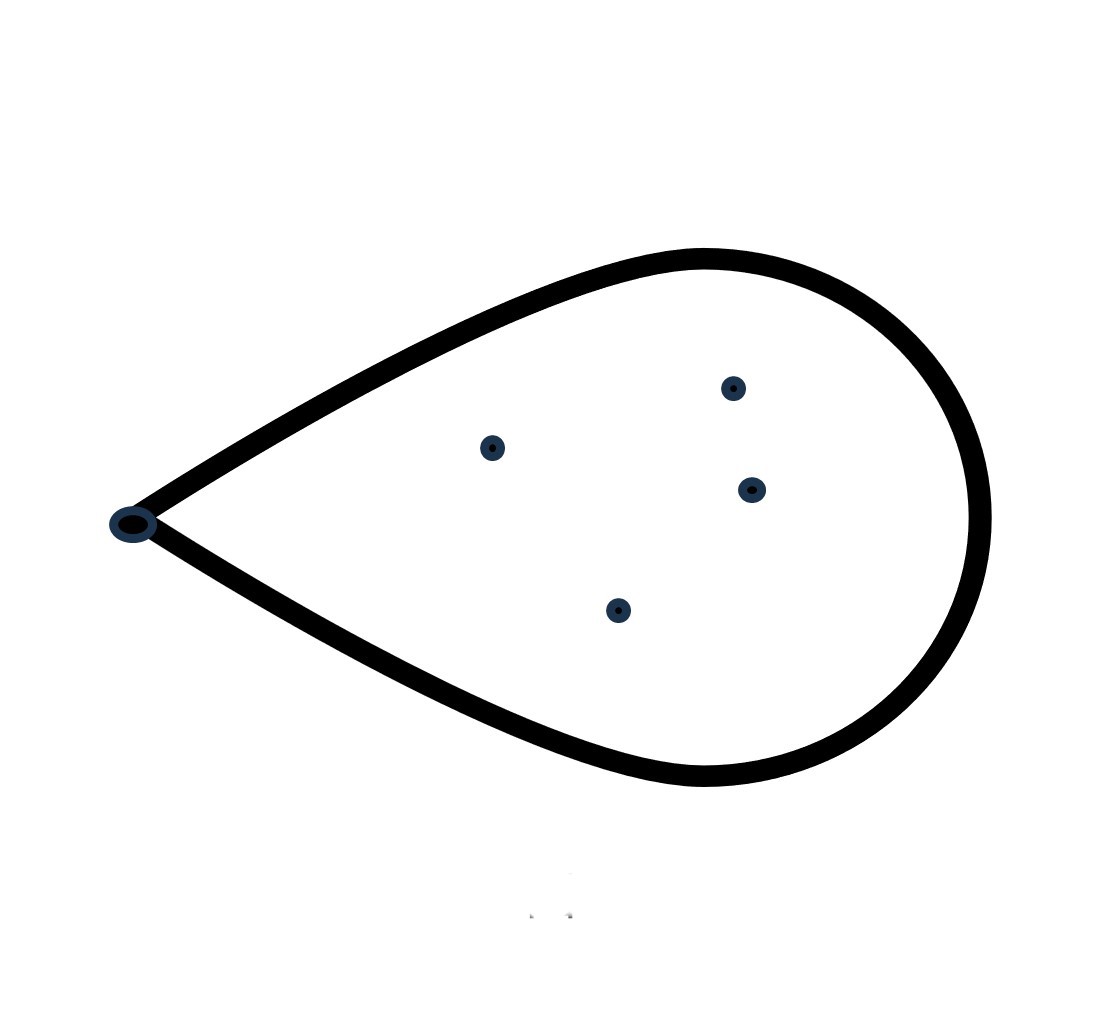| �Ⴆ�A�c�t���̍���ŁA����2�l���ꏊ�̎�荇���ő����Ă����Ƃ��܂��B�u�����͉����ŏ��ɗ������炨�O�͌������֍s���[�v�u����I�����͍�������������ƈꏏ�ɁA���܂܂��Ƃ����Ă�������ˁ[�v�ƁA����2�l�̉����͐^���ł��B�ł����̗l�q���l�����Ă������ɂ́A��������Ȃ��悤�Ɍ����A���|��������Ƃ�����u���܂��Ȃ��ŁA���ǂ��ˁ[�v�ʂł��傤���B
������3�̔���������܂��B�@�u�����͉����ŏ��ɗ������炨�O�͌������֍s���[�v�A�u����I�����͍�������������ƈꏏ�ɁA���܂܂��Ƃ����Ă�������ˁ[�v�B�u���܂��Ȃ��ŁA���ǂ��ˁ[�v��3�ł����A�����S�Ă��A�̐��E�ł̕\���ɂȂ�܂����A�Ō�̈�����́A�����̐��E�ł̕\���ł��ŏ���2�Ƃ͈���������ɂȂ�ł���H�q���̎��_�ł͂Ȃ��A��l�̎��_�ł̕����̌����ł��B
��������ꂸ�ɕ\������̂ł���A���̗����ł́A�ʏ�̂��̐��͇@�ƇA�̑��ΐ��E�̓̐��E�ςł��B���������̐��̒��ɂ́A�̐��E�ς̐l����ł͂Ȃ��A���܂Ɉꌳ�̐��E�ς̐l������̂ł��ˁB���m�N�w�̐��E�ł́A���̋��n��s��ꌳ�ƕ\�����Ă���悤�ł��B����́A�@�ƇA�������Ă��Ă��A�B�̂悤�Ɍ����Ď��炻�̑����ɉ���邱�Ƃ͂Ȃ��A���̑����ɑ��Ă����̂Ȃ����E�ς̏Z�l�ƌ�����ł��傤���B�����ĉ��Ɋ������܂ꂽ�Ƃ��Ă��A���킸�ɂ���������܂��B
�ł��̂ŁA���̐��E�ł̕\���Ƃ��Ă͑S�ċ��ʂ̌��t���g���̂ł����A�s��ꌳ�̐��E�ς̐l�̎g���\�����A�ʏ�͓̐��E�ς̐l�ɂ͗������ɂ����Ȃ�Ǝv���܂��B���x����́A��l�̕\�����邱�Ƃ��q���B�ɂ͗������ɂ����悤�ɂł��B�u���̍��ꂾ�v�u�������܂܂��Ƃ��v�Ƒ����Ă��鉀���ɑ��āu���ǂ��ˁv�����̈Ӗ������Ƃ��ė������ɂ����̂Ɠ��������낤�Ǝv���܂��B
�Ⴆ�u���Ȃ��͂ǂ����痈���̂ł����H�v�Ƃ����₢�ɑ��Ēʏ�̓̐��E�ς̐l���m�ł���u�D�y����A��ォ��A�v���Ă��痈�܂����[�v�ʼn�b�͐������܂����A�ꌳ�̐��E�ς݂̂̐l�Ȃ�u���́A��ɂ����ɂ��܂��v�Ƃ�������ɂȂ肻���ł��B����́A�Ⴆ�ꏊ�I�ɑ��Ⓦ�����猻�n�ɗ��Ă��悤�Ƃł��B
�ς�����Ƃ���ł́u���́A���Ȃ��ł��v�u��ɂ��đ��v�u�����Ȃ���ɂ��Ď���ł��܂��v���X�A�����̕\���������������Ƃ�����܂����A�����͑S�ĕs��ꌳ�̐��E�ςł̕\���ł��ˁB�L���Ȑl���ł����̋��n�Ȃ낤�Ȃ��Ǝv��������A�N�w�҂ł����Ȃ��炸������悤�Ɏv���܂��B
�����āA���̕s��ꌳ�����������n���s��s��̋��n�ɂȂ�܂��B���̋��n�ł́A�قړ̐��E�ς̐l�Ƃ̉�b�͐������Ȃ��ł��傤�B�u�����Ƀ����S������܂��ˁH�v�Ƃ����₢�����Ɂu����͂���̂ł͂Ȃ��A�����̂ł��Ȃ��v�u�E�E�E�v�u�ł́A��������̂ł����H�v�Ƃ����ēx�̖₢�ɂ́u����������̂ł͂Ȃ��A�Ȃ��̂ł��Ȃ��̂ł��B������܂��H�v�u�E�E�E�v�ƂȂ�ł��傤���B��荇�����������������ɂł������̂ł���A�ʏ�́A�X���[���������߂ł��傤�B�i�j���X�ⓚ������Ă��A�����A�̐��E�ς̐l�����߂铚���͓����܂���B���������̋��n���A�L�̐��E�ł̍ō��̋��n�Ƃ����L���V�Ƃ������n�̂悤�Ȃ̂ł��ˁi�j�ʌď̂ŁA��z���z���̋��n�ł��B�����̒��_��������Ƃ�����̂́A���̂��߂��Ǝv���܂��B
�����@�͏Ȃ��܂������A�s��ꌳ�ƕs��s��̈Ⴂ�̎����ł̐����ɂȂ�܂����B
���ԐM�́A�s�v�ł��B^^
|