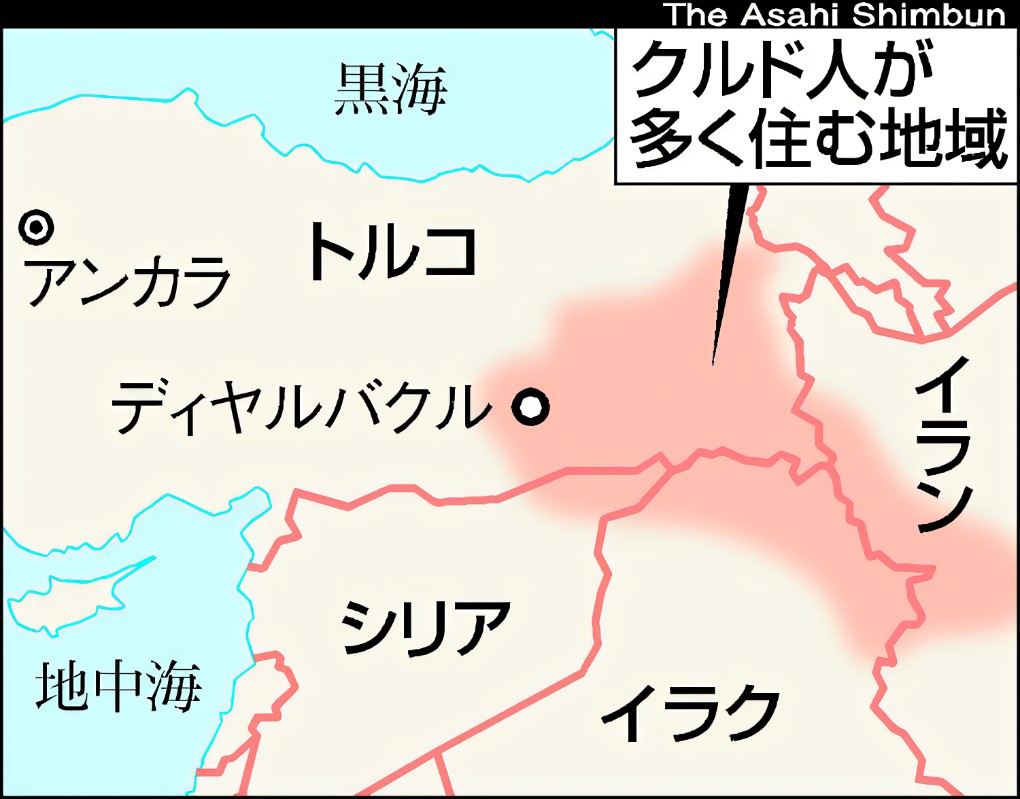| おはようございます、悪魔ちゃん
田総研掲載の悪魔ちゃん注目の箇所は外交の変容を述べた部分です。レポート提出のつもりでこの部分を要約してみます。悪魔ちゃん先生、宜しくお願いします!
ナポレオン戦争後ウィーンで会議が開かれ(1814〜5年)そこで国家間のバランスを維持し戦争の勃発を防ぐことが話合われました(ウィーン会議)。戦争になる前に話し合おうということで(ウィーン体制)、この時代の外交を「古典外交」と呼び、同質性、貴族性、自立性という特徴で表すことができます。
同質性というのは、同じ欧州内の国ということ(欧州文化というものを共有する)、貴族性というのは、外交上の言葉はフランス語で作法は貴族社会のもの(貴族の外交官も多かった)、自立性というのは、他を圧倒する国が存在せず各国が自立して勢力均衡を保っていたことを指します。
その後政治体制は近代的な官僚制となり国民の地位は向上し(国民国家)貴族性は失われていきます。アメリカや日本の台頭により同質性も失われ、また第1次世界大戦に向かって欧州内の2極化が進み各国の自立性が失われて行きました。このように第1次世界大戦の時にはいわゆる「古典外交」は既に終焉を迎えていました。
悪魔ちゃんの素晴らしい所
1.素朴に疑問を持つ
2.謙虚に研鑽する
ガンバロー!
|