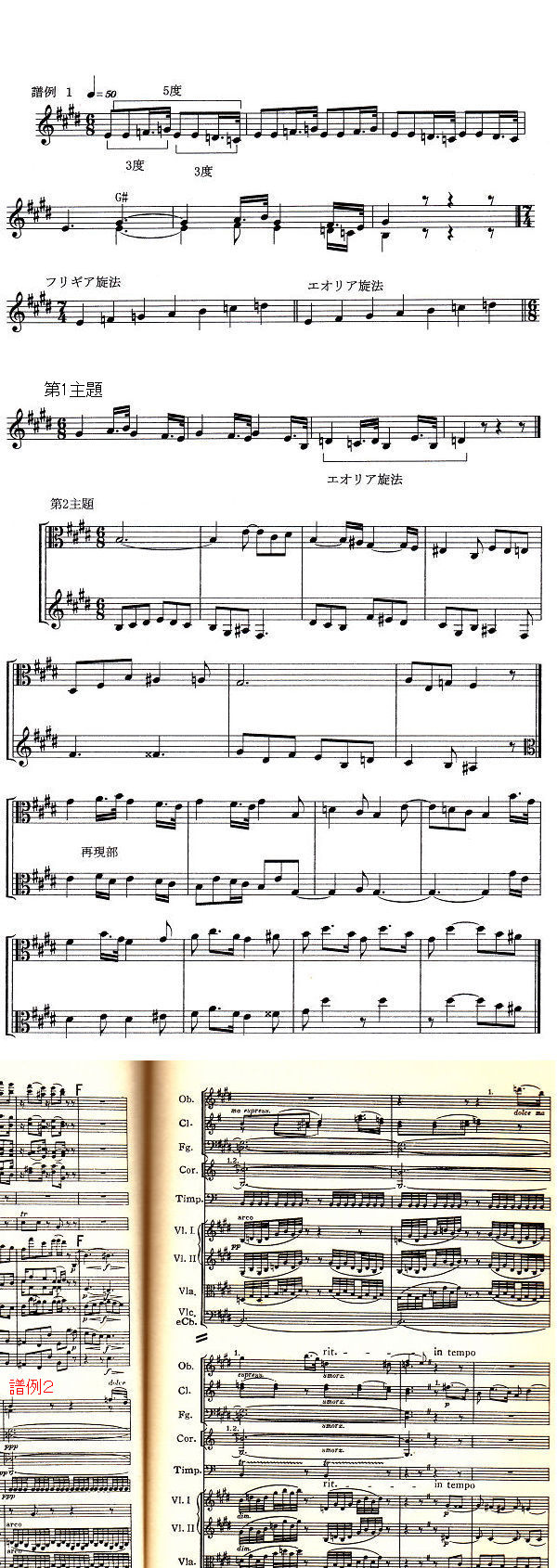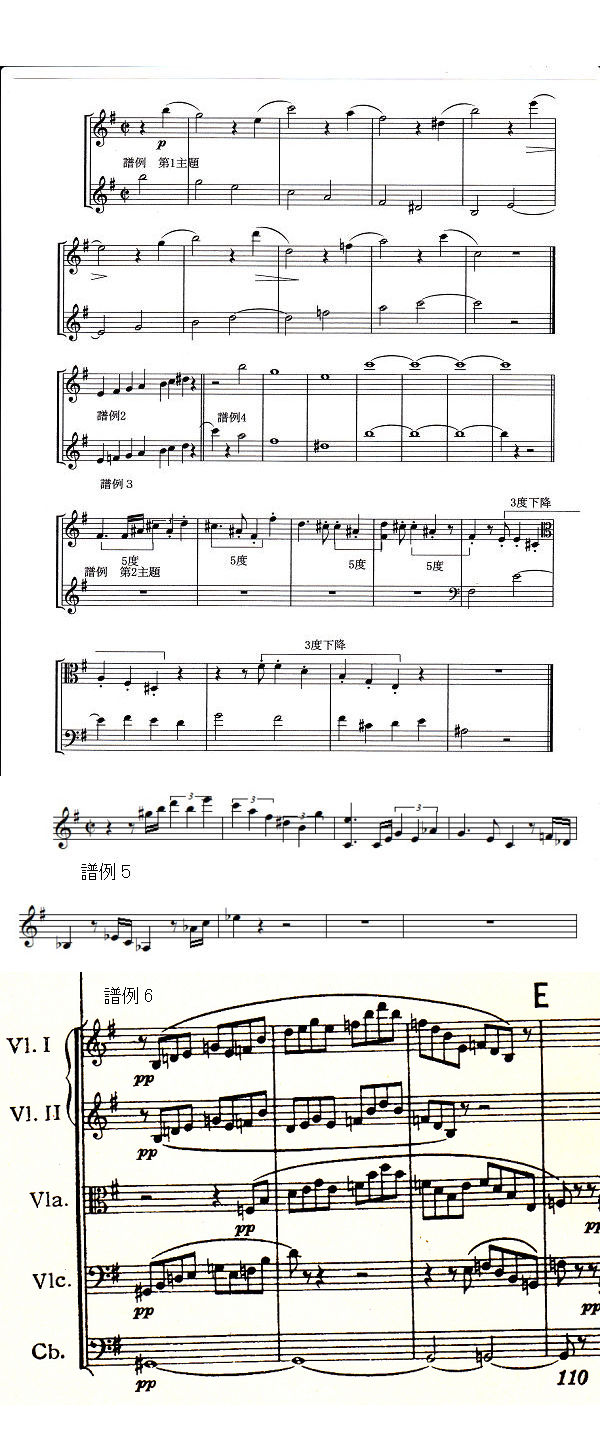| knowing itselfさんがギリシャ悲劇を持ち出されていたので、私はどの物語が好きなのか、考えてみました。ギリシャ悲劇に精通しているわけでも、数を知っているわけでもないのですが、やはりソポクレスの『オイディプス王』『クロノスのオイディプス』と『アンティゴネ』の三部作が好きです。
皆さん、ストーリーはご存じだと思いますので、すごく大雑把に書きますが、アポロンの神託を無視したばかりにオイディプスは実の父を殺し、実の母と結婚してテーベの王になる、が、自分の出生の秘密を知らされ母は自殺、オイディプスと自分の眼をつぶして乞食になってアンティゴネと旅に出る。クロノスへ行けとの神託を受け、アンティゴネとクロノスへ行き、森へ入りそこで命が尽きる、一方彼の二人の息子たちは、兄のエテオクレスが弟ポリネイセスをテーベから追い出す。が弟は軍を率いてテーベへ向かい兄と相打ちをして双方が死す。。アンティゴネはポリネイセスをテーベで弔って欲しいと願うが却下される、しかし遺体に砂をかけ弟を弔う。投獄され、アンティゴネは自害する。
アポロンの神託を無視したばかりに、子の代までに悲劇が襲う・・・紀元前5世紀にすでに立派なストーリーが組み立てられていたんですね・・・
シェークスピアが題材にしなかったのが不思議なくらいです。
|